Language
العربية
中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese
English
Français
Deutsch
Italiano
Bahasa Indonesia
日本語
한국어
Português
Русский
español
Tiếng Việt
Country/Area

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau
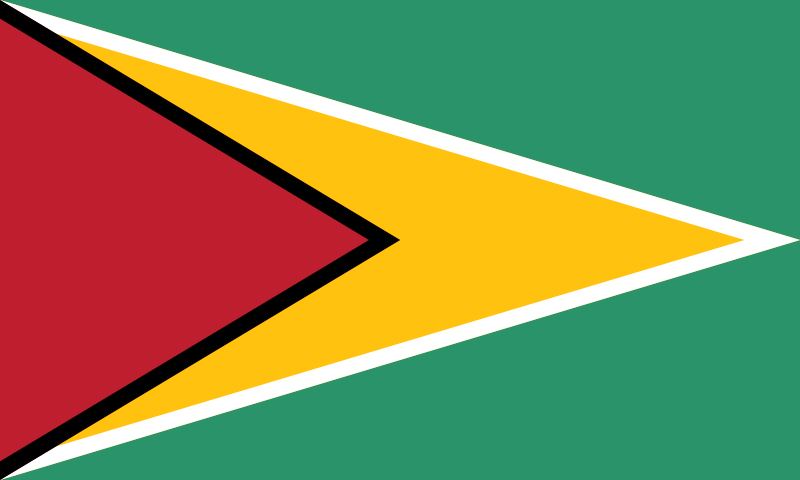
Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe
العربية
中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese
English
Français
Deutsch
Italiano
Bahasa Indonesia
日本語
한국어
Português
Русский
español
Tiếng Việt

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau
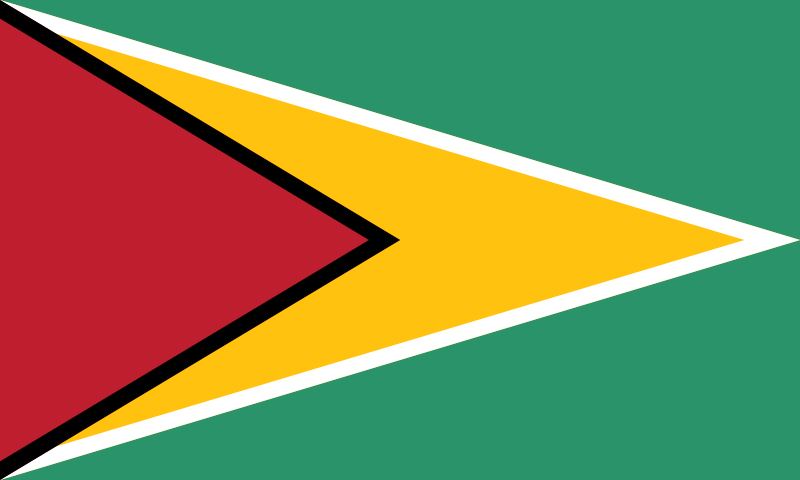
Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe
No result found
記憶のランドマーク:フランスの記憶の場所はなぜ私たちにとってそれほど重要なのか?
今日の社会では、記憶のランドマーク(lieux de mémoire)の概念が文化遺産の中心的な考え方となり、特定の歴史的出来事、人物、またはシンボルが社会にもたらす記憶を表しています。フランスの歴史家ピエール・ノラは、3巻からなる著書『記憶の野原』の中でこの概念を詳しく説明し、これらのランドマークは物理的な空間であるだけでなく、象徴的な意味を担うものでもあると指摘した。
「記憶のランドマークとは、物質的か非物質的かを問わず、人間の意志や時間の経過によって、あらゆるコミュニティの記念遺産の象徴的な要素となった重要な存在です。」
ノラの定義によれば、これらのランドマークには、記念碑、博物館、またはフランスのマリアンヌの像や植民地時代の赤旗などのイベントやシンボルが含まれます。その過程で、それらは国民の記憶の一部となり、過去と現在を結びつけ、人々が共通の歴史の重要性を理解し、振り返ることを可能にします。
フランスとケベックの共同委員会では、これらの記憶のランドマークをマッピングし、体系化することで、これらの空間の認知範囲を拡大し、社会の集合的な歴史の記憶を活性化することを目指しました。これらのランドマークの研究は、単一の文化の範囲に限定されるのではなく、世界中で同様の記憶の場所を見つけて再現することも目的としています。
「記憶のランドマークは、自然であると同時に人工的であり、単純であると同時に曖昧な複雑な存在です。」
しかし、記憶のランドマークとして、その存在は多くの方面から批判されてきた。学者のスティーブン・レッグは、ノラの記憶観は公式の歴史によって隠された受動的な状態であり、つまり歴史の公式な形成は地域の記憶の均質化につながると示唆している。同氏は「過去には国家の物語は一つで、個人の記憶も多かったが、今は国家の記憶は一つしかない」と指摘した。こうした統一化はむしろ、多くの地域固有の記憶の軽視につながっている。
ノラを支持する学者たちは、この概念は記憶と特定の場所との密接なつながりを強調しているため、理にかなっていると主張している。こうした評価は、歴史記憶における「社会的忘却」についての重要な議論を引き起こした。南アフリカの歴史家ガイ・ベナは、忘れ去られた記憶の場所の研究は、記憶に関する個別の視点のバランスをとるのにも役立つと主張している。
「国家建設の重要な部分として、祝日は国家のシンボルを形作り、正当化し、国家のアイデンティティと社会的結束を促進することができます。」
たとえば、祝日は記憶のランドマークとなることが多く、特定の歴史的出来事の記憶を保存するだけでなく、公の英雄に対する集団的な崇拝を育みます。これらの祝日の配置は歴史の認識と物語を反映しており、ある程度、その国が過去をどう捉えているか、そしてその過去が現在の社会構造にどう影響しているかを反映しています。
記憶に残る名所を探索するとき、私たちはこれらの場所が私たちの生活とどのように関係しているのか考えずにはいられません。グローバル化が進む中で、私たち自身の文化におけるこれらのランドマークの価値と重要性をどのように保存し、確立できるでしょうか?未来の秘密も私たちの歴史と記憶の中に隠されているのでしょうか?



