Language
العربية
中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese
English
Français
Deutsch
Italiano
Bahasa Indonesia
日本語
한국어
Português
Русский
español
Tiếng Việt
Country/Area

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau
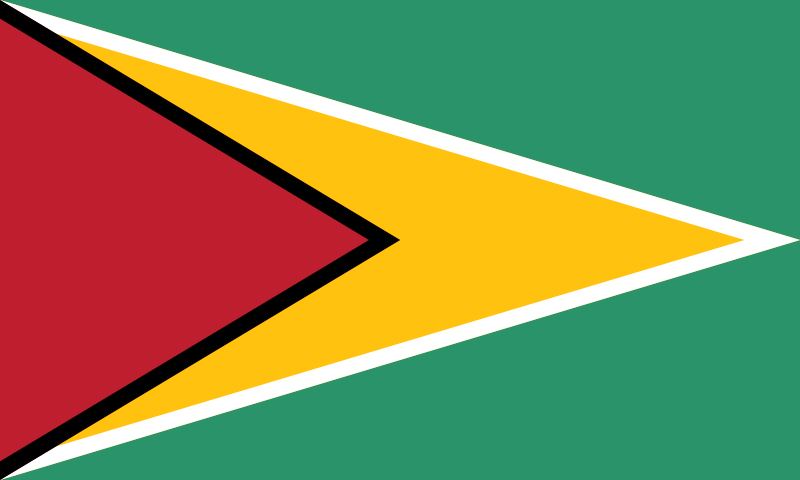
Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe
العربية
中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese
English
Français
Deutsch
Italiano
Bahasa Indonesia
日本語
한국어
Português
Русский
español
Tiếng Việt

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau
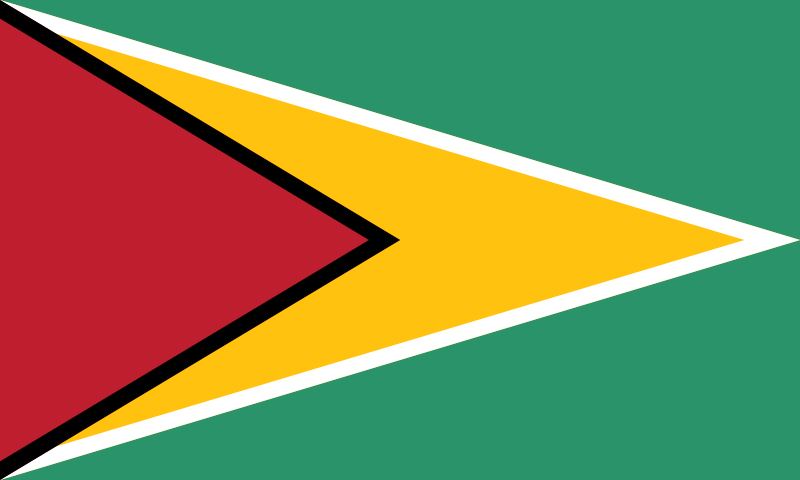
Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe
No result found
生態経済学の神秘的なルーツ:19 世紀のロマン主義からどのように生まれたのか?
生態経済学は単なる学問ではありません。経済学と生態学を組み合わせて、人間の経済システムと自然の生態系の相互依存性を探ります。この分野は 1980 年代以降に登場し、多くの学者に深い影響を受けてきましたが、そのルーツは 19 世紀のロマン主義運動にまで遡ることができます。
生態経済学は、自然、正義、時間に焦点を当て、世代間の公平性、環境変化の不可逆性、長期的な結果の不確実性、持続可能な開発を重視します。
生態経済学と環境経済学には明確な違いがあり、前者はどのような経済行動が生態系の長期的な安定性を支えることができるかに重点を置いています。環境を経済の付属物とみなす従来の環境経済学とは異なり、生態経済学では、経済システムをより大きな生態系システムのサブシステムとみなします。この概念はロマン主義の思想に由来しています。
エコロジカル経済学が形成された背景を理解するには、トーマス・マルサスやジョン・スチュアート・ミルなどの思想家が天然資源の不足と、食料安全保障の人気の高まりについて懸念を表明した19世紀のロマン主義運動を探る必要があります。深い理解。こうした視点を通じて、生態経済学は徐々に独自の枠組みを獲得してきました。
マルクス経済学者も資本と生態系の関係について深く考察し、その見解はエコ社会主義として知られるようになりました。
生態経済学の考え方は、特にニコラス・ジョルジェスク・ローガンとハーマン・デイリーの研究によって 1970 年代に近代化されました。二人の学者は、経済的な生産と消費の物質とエネルギーの流れは、お金という抽象的な概念で分析されるよりも重要であり、生態系に回復不可能なダメージを与えないように資源の使用を制限しなければならないと指摘した。
重要なのは、この考え方が生態学的バランスの維持を重視し、人工資本が自然資本に取って代わることができるという見解に反対していることです。ジョルジェスク=ローガンの文献を例に挙げてみましょう。彼の代表作『エントロピーの法則と経済過程』では、経済における物質の流れとエネルギーの流れの重要性について詳しく論じられています。
主流の資源経済学からより急進的な社会生態経済学まで、この分野で徐々に現れてきたさまざまな学派は、生態学と経済の関係についての異なる理解を反映しています。
たとえば、新エネルギー経済学者やグリーン経済学者は再生可能資源の利用と公平な配分を重視しますが、社会生態経済学者は生態学的限界と社会正義を重視します。これらの意見の相違は、成長を継続すべきかどうかについての異なる見解から生じており、一方、生態経済学では、天然資源の有限性と環境に配慮した経済行動を考慮しなければならないと主張している。
多様化した生態経済学では、非伝統的な経済概念がますます受け入れられるようになっています。その中で、E.F.シューマッハーの著書『スモール・イズ・ビューティフル』は、東洋の経済思想、特に仏教経済学の見解を紹介し、自然の調和の重要性を強調しました。この考えは、人間と自然の調和のとれた共存を強調する南米の「グッドライフ」運動でさらに広まりました。
生態経済学の教育は知識の普及に限定されるのではなく、自然環境との有意義な関係の構築にも重点を置いています。
生態経済学と主流経済学の最大の違いは、生態経済学では人間の相互作用による生態学的フットプリントを詳細に調査し、地球規模で資源の持続可能性を確保するためにこのフットプリントを最小限に抑えようとすることです。このような背景から、気候変動の問題は今日世界が直面している最も差し迫った課題の一つとなり、より深い学術的議論と政策立案を引き起こしています。
現在、生態経済学の将来は課題に満ちており、この分野の継続的な発展が、特に資源枯渇と生態系の劣化に直面している現在の環境危機を解決するための効果的な対策を提供できるかどうかは、依然として困難な課題です。 。 の。
私たちの未来が自然と調和して共存できるように、生態学と経済のバランスをとることはできるでしょうか?



