Language
العربية
中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese
English
Français
Deutsch
Italiano
Bahasa Indonesia
日本語
한국어
Português
Русский
español
Tiếng Việt
Country/Area

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau
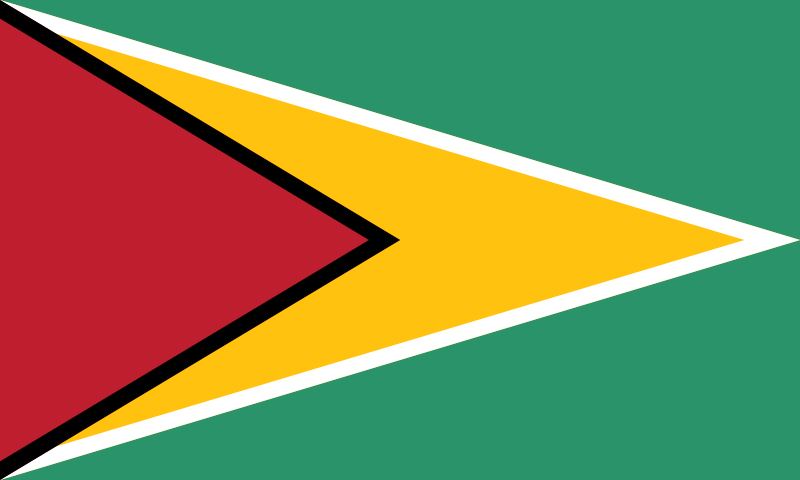
Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe
العربية
中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese
English
Français
Deutsch
Italiano
Bahasa Indonesia
日本語
한국어
Português
Русский
español
Tiếng Việt

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau
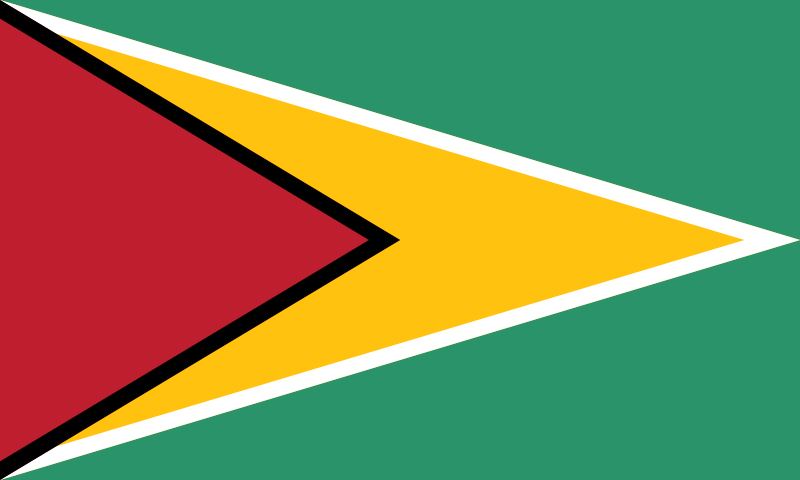
Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe
No result found
組織理論では、組織ルーチンは、複数の主体によって実行される相互依存的なアクションの反復可能で識別可能なパターンとして定義されます。これらのルーチンは、日常業務の単なるステップではなく、組織がどのように運営され、適応し、変化するかを理解する上で中核的な要素です。従来、学者は組織ルーチンをさまざまな方法で捉えており、組織ルーチンを安定化要因と見なす人もいれば、組織変化の原動力と見なす人もいます。この二重性により、組織のルーチンは管理分野で引き続き研究される注目のテーマとなっています。
組織のルーチンは、生物学的遺伝子と同様に遺伝性があり、環境選択の影響を受けます。
組織ルーチンの基本
20 世紀の初めには、カーネギー学派は組織行動における習慣の概念を掘り下げ始めました。この考え方によれば、個人の行動は合理的に制限されるため、組織は意思決定プロセスをより効率的にするルーチンを開発します。これらのルーチンは組織内の活動を調整および制御し、組織が外部環境の変化に迅速に対応できるようにします。
ルーチンは実際には組織の記憶、特に明示的にエンコードされていない暗黙知です。
安定と変化の源
本質的に、組織ルーチンは、組織のメンバーが特定の行動規範に依存して日常業務を遂行できる安定した運用モデルを提供します。しかし、これは組織が変化に抵抗する可能性も高くなります。組織のルーチンは両刃の剣のようなもので、イノベーションや変化を推進できなければ、大きな障害となります。
日常的なパフォーマンスに慣れていると、周囲の環境の変化を感知できなくなる可能性があります。
組織の日常的な行動パターン
組織のルーチンを研究すると、それが単なる単純な操作手順ではなく、社会的な相互作用や行動の複雑なパターンも含まれていることがわかります。これらのパターンは、個人の習慣だけではなく、ある程度集団的な行動の産物です。このため、組織におけるルーチンの永続と変革は継続的な議論の対象となっています。
個人の行動の役割
組織では、個々の役割と責任により、実際の日常的な行動は人によって異なる場合があります。これは、場合によっては従業員がルーティンから抜け出し、より効率的な働き方を模索する理由も説明できます。この行動は、日常生活の変化としてだけでなく、現状への挑戦としても見られます。
変化の主体
私たちの観察から、内部管理の変更であろうと外部環境の課題であろうと、組織のルーチンは長期にわたって静的な状態を維持できないことがわかります。ルーティンの進化には組織的な学習が伴うことが多く、これは過去の経験を振り返るだけでなく、将来の不確実性に適応するために必要なプロセスでもあります。
ルーチンは行動の文法と考えることができ、ルーチンを選択して実行するのは骨の折れる作業です。
将来について考える
絶え間なく変化するビジネス環境に直面して、組織の日常業務の二重の性質を理解することが特に重要です。これは、企業が自社の内部プロセスが厳格すぎるかどうかを評価するのに役立つだけでなく、イノベーションの能力も高めます。組織の将来を考えるとき、これらの一見安定したルーチンを再評価し、安定性を維持しながら変化を促進する方法を検討する必要があるでしょうか。



