Language
العربية
中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese
English
Français
Deutsch
Italiano
Bahasa Indonesia
日本語
한국어
Português
Русский
español
Tiếng Việt
Country/Area

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau
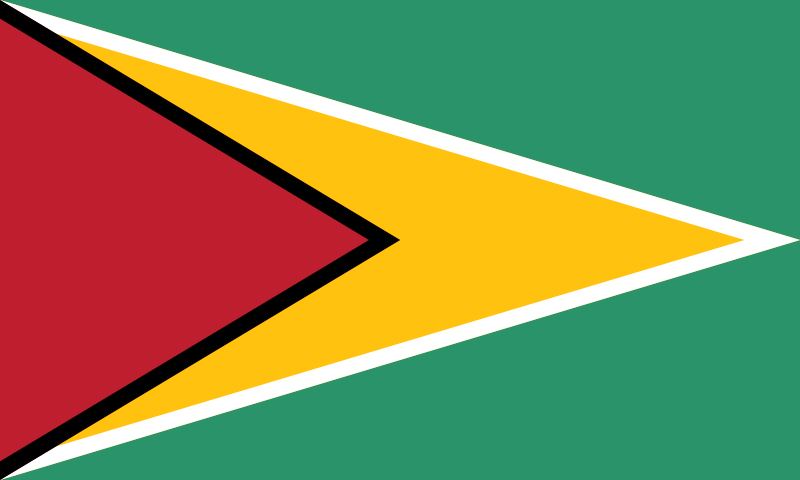
Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe
العربية
中文

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Traditional Chinese
English
Français
Deutsch
Italiano
Bahasa Indonesia
日本語
한국어
Português
Русский
español
Tiếng Việt

افغانستان

Shqipëri

الجزائر

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Հայաստան

Australia

Österreich

Azərbaycan

The Bahamas

البحرين

বাংলাদেশ

Barbados

Беларусь

België

Belize

Bénin

འབྲུག་ཡུལ་

Bolivia

Bosna i Hercegovina

Botswana

Brasil

Negara Brunei Darussalam

България

Burkina Faso

Uburundi

Cape Verde

កម្ពុជា

Cameroun

Canada

République Centrafricaine

Tchad

Chile

中国

Colombia

Komori

République Démocratique du Congo

République du Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Hrvatska

Cuba

Κύπρος

Česká republika

Danmark

جيبوتي

Dominica

República Dominicana

Timor-Leste

Ecuador

مصر

El Salvador

Guinea Ecuatorial

ኤርትራ

Eesti

Eswatini

ኢትዮጵያ

Fiji

Suomi

France

Gabon

The Gambia

საქართველო

Deutschland

Ghana

Ελλάδα

Grenada

Guatemala

Guinée

Guiné-Bissau
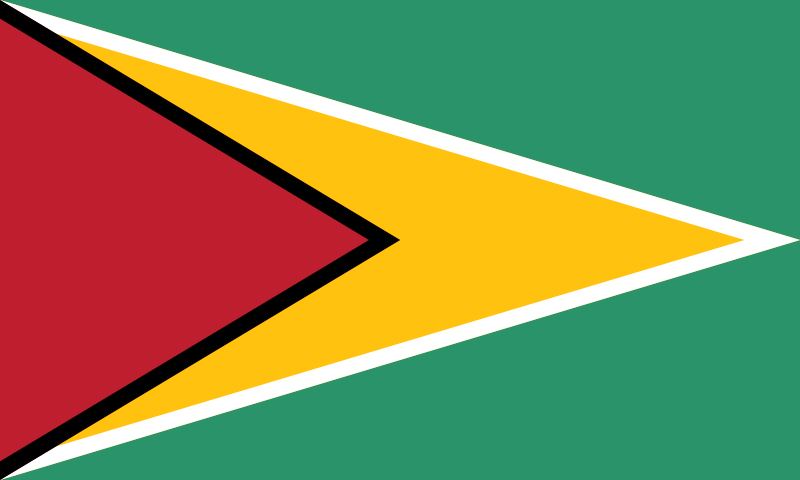
Guyana

Haïti

Honduras

香港

Magyarország

Ísland

भारत

Indonesia

ایران

العراق

Éire

ישראל

Italia

Jamaica

日本

الأردن

Қазақстан

Kenya

Kiribati

조선

대한민국

Kosovë

الكويت

Кыргызстан

ປະເທດລາວ

Latvija

لبنان

Lesotho

Liberia

ليبيا

Liechtenstein

Lietuva

Lëtzebuerg

Madagasikara

Malawi

Malaysia

ދިވެހިރާއްޖެ

Mali

Malta

Aolepān Aorōkin M̧ajeļ

موريتانيا

Maurice

México

Micronesia

Moldova

Monaco

Монгол Улс

Crna Gora

المغرب

Moçambique

မြန်မာ

Namibia

Naoero

नेपाल

Nederland

Aotearoa

Nicaragua

Niger

Nigeria

Северна Македонија

Norge

عمان

پاکستان

Belau

Panamá

Papua Niugini

Paraguay

Perú

Pilipinas

Polska

Portugal

قطر

România

Россия

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

São Tomé e Príncipe

المملكة العربية السعودية

Sénégal

Србија

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovensko

Slovenija

Solomon Islands

Soomaaliya

South Africa

España

ශ්රී ලංකාව

السودان

جنوب السودان

Suriname

Sverige

Schweiz

سوريا

臺灣

Тоҷикистон

Tanzania

ประเทศไทย

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

تونس

Türkiye

Türkmenistan

Tuvalu

Uganda

Україна

الإمارات العربية المتحدة

United Kingdom

United States

Uruguay

O‘zbekiston

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Việt Nam

اليمن

Zambia

Zimbabwe
No result found
ガブリエル・ガルシア=マルケスの『百年の孤独』は、架空の町マコンドの運命を描いています。この町とその住民は、創設以来の運命に縛られ、破滅へと運命づけられています。この小説では、マコンドの盛衰は個人の運命を反映しているだけでなく、ラテンアメリカの歴史と文化の縮図でもあります。この宿命論的な感覚はどこから来るのでしょうか?
歴史は繰り返すマコンドの運命は逃れようがなく、過去に支配されており、時間の複雑さにより、登場人物が歴史の繰り返しから逃れることは不可能である。
『百年の孤独』では、マコンドとその住民は目に見えない力に縛られ、家族の運命から逃れることができません。物語では、ブエンディア家の7世代が度重なる悲劇に巻き込まれ、本当の救いを見つけることができません。この悲劇は個人の運命の悲劇であるだけでなく、町全体の運命を反映したものでもある。当初、マコンドは理想的なユートピアとして描かれていましたが、時が経つにつれて、この美しい幻想は徐々に崩壊し、最終的には跡形もなく消えてしまいました。
運命のささやき
マルケスは魔法のリアリズムを巧みに利用して歴史とファンタジーを融合させ、運命の存在を表現しています。ホセ・アルカディオ・ブエンディアなどの小説の登場人物は、宇宙の謎を探求することへの執着によって気が狂ってしまいます。この狂気は、自らの運命をコントロールできない人間の無力さを反映している。このような環境の中で、マコンドの住民は運命に操られる操り人形のような存在だ。彼らの歴史は過去への郷愁と未来への混乱に満ちており、最終的には無慈悲な時の流れによって消し去られてしまう。
マコンドはより良い世界の追求を象徴していますが、歴史の展開により残酷に否定されています。
マコンドの独立と衰退
マコンドが徐々に外の世界と接触するにつれ、新しいアイデアや技術の導入は町に繁栄をもたらしたように見えたが、実際には町の破壊を加速させた。アメリカのバナナ会社は農園を開設し、独自の社会構造を導入したが、その繁栄は土地の強奪と労働者の搾取という代償を伴っていた。労働者が権利を求めて闘うと、守備隊によって虐殺された。この事件はマコンドの歴史における大きな悲劇となり、自由の幻滅を象徴するものとなった。
イデオロギーの束縛
この小説では、ラウル・アウレリャーノ・ブエンディアは革命家であり、その戦いは自由と変化への欲求を表していますが、最終的には信念を失い平和を選択します。この無力感はマコンドの歴史の避けられない運命を反映している。登場人物の選択や行動は運命によって決められているようで、どんなに努力しても結局は影のように付きまとう歴史の重荷から逃れることはできない。
『百年の孤独』では、運命の概念は個人の運命を反映するだけでなく、繰り返される悪夢のように、国家全体の歴史も反映しています。
マコンドの失踪
小説の最後では、マコンドはブエンディア一族の最後の一人の死とともに姿を消す。これは個人や家族の終わりであるだけでなく、町全体の運命の象徴でもあります。マコンドの破壊は人類の歴史の悲劇的な循環を意味している。それが歴史の繰り返しによるものなのか、それとも避けられない宿命論によるものなのかはわからないが、読者に深い後悔の念を抱かせる。
『百年の孤独』の結末は、ある種、詩的な絶望感に満ちており、人々に疑問を抱かせる。これほど長い歴史の中で、運命を破る行動は本当に存在するのだろうか、それとも、すべては既に運命づけられているのだろうか。逃れられない?運命?



